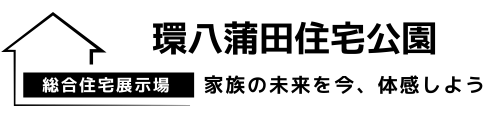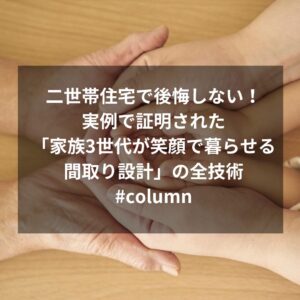【実証済】ペット共生住宅で抜け毛が床に散らばらない!専門家が教える間取りの秘密#column
この記事を読めば分かること
この記事では、犬や猫と快適に暮らすための家づくりの具体的なノウハウをお伝えします。滑りにくい床材の選び方、ペット専用スペースの作り方、臭い対策の実践方法、そして実際の施工事例まで、中学生でも理解できるように分かりやすく解説します。読み終わる頃には、あなたの愛するペットと家族全員が笑顔で過ごせる理想の住まいのイメージが、はっきりと頭の中に浮かんでいることでしょう。
はじめに
窓辺で気持ちよさそうに寝転がる愛犬の姿を見て、あなたは微笑んでいます。リビングのキャットウォークでは、愛猫がしなやかに体を伸ばしながら、あなたを見下ろしています。家族全員が、そしてペットたちも、心からリラックスできる空間——それが、これからあなたが手に入れる「ペットと暮らす家」です。
でも現実には、フローリングで滑って転びそうになる愛犬、壁で爪を研いでボロボロになった壁紙、部屋中に漂うペット特有の臭い……。こんな悩みを抱えている飼い主さんは少なくありません。
実は、家を建てる時やリフォームする時に、ほんの少しの工夫をするだけで、これらの悩みはすべて解決できるのです。この記事では、犬や猫の生態を理解した上で、飼い主もペットも両方が快適に過ごせる住まいづくりの秘訣を、具体的な事例とともにお伝えします。
ペットは家族の一員です。だからこそ、人間だけでなくペットにとっても居心地の良い空間を作ってあげたいですよね。さあ、理想の「ペット共生住宅」への第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
犬と猫、それぞれの「好き」を知ろう——ペットの特徴を理解する
犬が本当に求めているものとは?
早朝の公園を想像してみてください。リードを引っ張りながら、嬉しそうに走り回る犬の姿が目に浮かびますよね。犬にとって散歩は、単なる運動ではありません。外の空気を吸い、太陽の光を浴び、他の犬と触れ合う——これらすべてが、犬の心と体の健康を保つために必要不可欠なのです。
だから家の中でも、自由に動き回れる空間が大切です。行き止まりのない回遊できる間取りにすれば、雨の日でペットが室内で運動不足になる心配もありません。また、窓から外の様子を眺められる場所があれば、お留守番の時間も退屈せずに過ごせます。
もう一つ、犬には意外な習性があります。それは「狭い場所が好き」ということです。犬の祖先はオオカミで、穴ぐらで暮らしていました。その名残で、現代の犬も家具の隙間やクレート(犬用のケージ)のような狭い空間に入ると、不思議と落ち着くのです。
雷が鳴った時、掃除機の音にびっくりした時、あなたの愛犬はどこに隠れますか?きっと、ソファの下やベッドの隙間など、狭くて暗い場所を選んでいるはずです。だから家づくりでは、犬が自由に出入りできる「秘密基地」のような空間を用意してあげましょう。
そして忘れてはいけないのが、犬は群れで生活する動物だということです。一人ぼっちは、犬にとって大きなストレスになります。お留守番の時に吠え続けたり、クッションを噛みちぎったりするのは、寂しさや不安の表れかもしれません。ペット用の見守りカメラを設置すれば、外出先からスマートフォンで愛犬の様子を確認できて安心です。
猫が求める「高さ」のある暮らし
猫がキャットタワーのてっぺんで、目を細めて気持ちよさそうにしている光景を見たことがあるでしょう。猫は、なぜこんなにも高い場所が好きなのでしょうか?
その答えは、猫の祖先にあります。野生の猫は狩りをして生きていました。高い木の上は、獲物を見つけやすく、敵に襲われる危険も少ない「特等席」だったのです。また、猫社会では、高い場所にいる猫ほど強い立場にあるとされています。だから家の中でも、高い場所は猫にとって「自分のお城」のような存在なのです。
キャットタワーがなくても大丈夫です。家具の配置を工夫して、猫が飛び移りながら高い場所まで登れるようにしてあげましょう。吹き抜けの梁を猫の通り道にしたり、壁に階段状の棚を取り付けたりするのもおすすめです。
窓辺で日向ぼっこをする猫の姿も、よく見かけますよね。日光浴は、猫にとって単なる趣味ではありません。太陽の光を浴びることで、免疫力が高まり、被毛(毛並み)も清潔に保たれます。さらに、日向ぼっこをした後はぐっすり眠れるという効果もあるのです。
南向きの大きな窓がある部屋なら、そこに猫専用のクッションを置いてあげましょう。窓から外を眺めながらお昼寝できる場所は、猫にとって最高の贅沢です。ただし、窓からの脱走を防ぐために、柵やネットを取り付けることを忘れずに。
最後に、猫の「爪とぎ」について。壁や家具で爪を研がれて、困っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。でも、爪とぎは猫の本能なので、やめさせることはできません。それどころか、ストレス発散やマーキング(縄張りを主張すること)の意味もあるので、猫の健康には必要不可欠な行動なのです。
大切なのは「やめさせる」のではなく、「やって良い場所を作る」こと。麻縄でできた爪とぎポールを用意したり、壁の一部を爪とぎ用のパネルで保護したりすれば、家を傷つけられる心配もありません。

ペットも人間も笑顔になる——快適な間取りの3つのポイント
ポイント1:ペットの性格に合わせた専用スペースを作る
あなたの家族が、それぞれ自分の部屋を持っているように、ペットにも専用の空間が必要です。ただし、犬と猫では求める空間が違います。
犬は「家族と一緒にいたい」生き物です。だから、リビングの一角に犬専用のスペースを作ってあげましょう。家族の気配を感じながら、安心して休める場所が理想です。階段下のデッドスペース(普段は使わない空間)を活用すれば、天井が低くて壁に囲まれた、犬が落ち着ける「秘密基地」になります。
一方、猫は「一人の時間も大切にしたい」生き物です。段ボール箱やキャリーバッグのような、すっぽり体が入る狭い空間を用意してあげましょう。人通りの少ない静かな場所に置けば、猫が他のペットや来客から身を隠したい時の避難場所になります。
トイレの場所も重要です。犬は排泄する時、無防備な姿勢になるので、少しでも隠れられる場所を好みます。猫はもっと神経質で、自分の寝床や食事場所から離れた、静かで人目につかない場所でないと安心して排泄できません。
トイレは、生活スペースから少し離れた場所に設置しましょう。掃除しやすい防水床にして、換気扇を取り付ければ、臭い対策もバッチリです。特に猫は綺麗好きなので、トイレが汚れていると病気になることもあります。毎日こまめに掃除できる場所を選ぶことが大切です。
ポイント2:毎日の掃除が楽になる工夫をする
ペットと暮らすと、掃除の手間が増えるのは避けられません。抜け毛、食べこぼし、トイレの失敗、散歩から帰った後の泥だらけの足……。一日に何度も掃除機をかけたり、雑巾がけをしたりするのは大変ですよね。
だからこそ、家を建てる段階で「掃除が楽になる工夫」を取り入れることが重要なのです。
まず床材選びです。普通のフローリングは、ペットの毛が絡まりやすく、傷もつきやすいです。ペット用に開発されたフローリングなら、表面に特殊な加工がしてあるので、汚れをサッと拭き取れます。また、タイルカーペットなら、汚れた部分だけを外して洗ったり、交換したりできるので便利です。
壁も同じです。ペット用の壁紙は、汚れが付きにくく、爪で引っかいても傷つきにくい素材でできています。もっと丈夫なものが良ければ、タイルもおすすめです。見た目もおしゃれで、インテリアのアクセントにもなります。予算を抑えたい場合は、ペットが届く高さだけ素材を変える「腰壁」という方法もあります。
散歩から帰った犬の足を、毎回洗うのも面倒ですよね。玄関のすぐ近くに足洗い場があれば、帰ってすぐに足を洗えるので、家の中に泥を持ち込まずに済みます。ペット用のシャワー設備なら、全身を洗うこともできます。夏は水遊び場としても使えますよ。
寒い地域に住んでいる場合は、玄関の中に足洗い場を作るのもおすすめです。冷たい水で足を洗うと、ペットの体が冷えてしまうので、お湯が使える設備にしましょう。
ポイント3:運動不足を解消できる動線を作る
元気いっぱいの犬や若い猫は、家の中でも走り回りたいものです。でも、狭い部屋や行き止まりの多い間取りでは、思うように動けません。
そこで取り入れたいのが「回遊動線」です。これは、ぐるぐると一周できる間取りのことです。たとえば、リビング→廊下→キッチン→リビングと、円を描くように移動できれば、ペットは家の中を自由に走り回れます。
壁にペット専用の小さなドア(ペットドア)を付ければ、人間がドアを開け閉めしてあげなくても、ペットが好きな時に通り抜けられます。スキップフロア(段差のある間取り)なら、壁やドアが少なくて済むので、ペットと家族がお互いの様子を見守れて安心です。
雨の日や暑い日、寒い日でお散歩に行けない時でも、家の中で十分に運動できる環境があれば、ペットのストレスも溜まりません。
ペットを守る——安全対策は命を守る大切なルール
危険な場所には絶対に入れない
家の中には、ペットにとって危険な場所がたくさんあります。特に気をつけたいのが、キッチン、お風呂場、そして玄関です。
キッチンには、コンロの火、包丁などの刃物、熱いお湯が入った鍋など、危険なものがいっぱいです。好奇心旺盛なペットがキッチンに入り込んで、火傷や怪我をしてしまう事故は少なくありません。
お風呂場も要注意です。浴槽に水を張ったままにしておくと、覗き込んだ時に落ちて溺れてしまう可能性があります。特に入浴剤を入れた水は、ペットが誤って飲んでしまうと体に害があります。入浴後は必ず水を抜いておきましょう。シャンプーや石鹸も、ペットが口にしないように、手の届かない高い場所に置いてください。
玄関も危険です。ドアを開けた瞬間、ペットが外に飛び出してしまうことがあります。車にひかれたり、迷子になったりする恐れがあるので、玄関にはペットフェンスを設置しましょう。
ペットフェンスは、置くだけで簡単に設置できるタイプがあります。ペットの大きさやジャンプ力に合わせて、高さを選んでください。キッチンやお風呂場、階段の入り口など、危険な場所の前に設置すれば、大切なペットの命を守れます。
滑る床は骨折の原因に
ピカピカに磨かれたフローリングは、見た目は綺麗ですが、ペットにとっては危険な床です。犬や猫の足の裏には肉球があり、人間のように靴を履いていないので、ツルツルの床では滑ってしまいます。
滑りやすい床で走り回ると、足腰に大きな負担がかかります。特に犬は、脱臼、骨折、椎間板ヘルニアなどの怪我をしやすくなります。年を取った犬や猫は、骨が弱くなっているので、さらに危険です。
滑りにくい床材としておすすめなのが、コルク材、タイルカーペット、そしてペット用のコーティングを施したフローリングです。これらはクッション性もあるので、足音も響きにくく、階下への騒音対策にもなります。
ペットが安心して走り回れる床を選ぶことは、怪我を防ぐだけでなく、ペットの生活の質を高めることにもつながります。
プライバシーも大切に——ペットにも「一人の時間」が必要
人間が一人になりたい時があるように、ペットにもプライバシーが必要です。
特に食事とトイレの時は、じっと見られると落ち着かないものです。人通りの少ない静かな場所に、ペット専用のコーナーを作ってあげましょう。
猫は特に、一人の時間を大切にする動物です。段ボール箱のような「隠れ家」を用意してあげれば、誰にも邪魔されずにリラックスできます。
犬は家族と一緒にいるのが好きですが、就寝時には専用のスペースで休ませてあげましょう。家族もペットも、それぞれがゆっくり眠れる環境を整えることが大切です。
臭いや音の悩みを解決——快適な空間を保つ秘訣
臭い対策は「素材選び」と「こまめな掃除」
ペットを飼っていると、どうしても気になるのが臭いです。家族は慣れてしまって気づかないかもしれませんが、来客の時に「ペットの臭いがする」と思われるのは嫌ですよね。
臭いの原因は、排泄物、餌の食べ残し、そしてペット自身の体臭です。これらの臭いは、時間が経つと壁や床に染み込んでしまいます。
臭い対策として効果的なのが、消臭機能のある壁紙や床材を使うことです。最近では、ペット用に開発された建材がたくさんあります。また、トイレの近くに換気扇を設置すれば、臭いがこもりません。
もちろん、こまめな掃除も大切です。トイレは毎日掃除する、ペットを定期的にシャンプーするなど、臭いの元を減らす努力も忘れずに。
鳴き声や足音の防音対策
夜中に犬が吠えたり、猫が走り回ったりすると、近所迷惑にならないか心配ですよね。特に集合住宅では、音のトラブルは避けたいものです。
音が最も漏れやすいのは窓です。防音性の高いサッシ(窓枠)に変えたり、防音カーテンを使ったりしましょう。既存の窓の内側にもう一枚窓を追加する「二重窓」も効果的です。窓の外にシャッターを付けて、夜は閉めておくという方法もあります。
足音対策には、カーペットやコルク材など、音を吸収する床材を選びましょう。硬いフローリングに比べて、足音がかなり静かになります。滑り止めの効果もあるので、ペットにとっても快適です。
実例に学ぶ——犬と暮らす家の間取りアイデア
広々土間とドッグランで毎日が楽しい
玄関の土間を広くすると、犬との暮らしがぐっと便利になります。散歩グッズやペットカート、おもちゃなどを収納できて、帰ってきた時に足を拭いたりブラッシングしたりするスペースとしても使えます。土間は汚れても水で流せるので、掃除も簡単です。
ある家では、玄関からリビングまで土間でつなげています。愛犬が散歩から帰ってきた時、そのまま土間を通ってリビングまで移動できるので、家の中を汚しません。土間は夏でもひんやり涼しいので、暑がりな犬にとっては快適なお留守番スペースにもなります。
庭にドッグランを作れば、雨の日以外はいつでも思いっきり走り回れます。フェンスで囲って安全を確保すれば、飼い主も安心です。リビングから続くウッドデッキで、家族も一緒にアウトドアリビングを楽しめます。
ぐるぐる回れる間取りで運動不足解消
「うちには広い庭がないから、ドッグランは無理……」という方でも大丈夫です。家の中を回遊できる間取りにすれば、室内でも十分に運動できます。
ある家では、アイランドキッチン(壁に接していないキッチン)の周りをぐるっと一周できる動線になっています。家族が家にいる時は、二箇所のペットフェンスを開放して、愛犬が自由に走り回れます。お留守番の時や来客時は、フェンスを閉めれば、キッチンなどの危険な場所に入れません。
愛犬専用の「犬土間」を作った家もあります。土間はウッドデッキに直結していて、遊んだ後はここで足を拭いたり、ご飯を食べたりします。掃除しやすく、汚れも気になりません。腰壁にはタイルを貼って、傷つき防止も万全です。
犬土間はリビングの横に配置して、建具(ドア)には顔を出せる小窓を付けました。これなら、愛犬も家族の気配を感じられて、寂しくありません。
大型犬も快適な土間サロン
バーニーズマウンテンドッグという大型犬と暮らす家では、大きな窓に面した土間サロンに、愛犬のくつろぎスペースを作りました。陽がたっぷり差し込む土間は、キャンプ道具の収納やメンテナンスをする場所としても活躍します。汚れが気にならず、お手入れも簡単です。
キッチン・ダイニングとつながった土間サロンなら、愛犬はいつも家族の気配を感じられて安心です。夜は、別のプライベート空間でゆっくり休みます。
10畳を超える広いウッドデッキは、飼い主の手作りです。薪棚に囲まれた庭で、愛犬と一緒に遊べます。
実例に学ぶ——猫と暮らす家の間取りアイデア
上下運動ができるキャットウォーク
猫は室内で飼うのが推奨されているので、運動不足やストレスを溜めないように、家の中に十分な運動スペースが必要です。
猫にとって大切なのは、広い場所よりも「高い場所」です。登ったり、ジャンプして飛び移ったりできる環境を整えてあげましょう。
キャットタワーを置くのが一番簡単ですが、吹き抜けの梁を猫の通り道にしたり、壁に階段状の棚(キャットステップ)を取り付けたりする方法もあります。家具の上を飛び移りながら、高い場所まで登れるように配置するのも良いアイデアです。
部屋全体を見渡せる高い場所に猫専用のスペースを作ると、来客や他のペットから適度な距離を保ちながら、安心して過ごせます。
爪とぎコーナーで壁を守る
猫が壁や家具で爪を研ぐのは、やめさせることができません。無理にやめさせようとすると、かえってストレスになります。
大切なのは、「爪を研いで良い場所」を作ることです。猫が好む素材の爪とぎポールを設置したり、いつも爪を研ぐ場所に麻縄パネルを貼ったりしましょう。移動できるタイプなら、猫のお気に入りの場所に置けます。
日向ぼっこスペースで健康管理
日向ぼっこは、猫の免疫力を高め、被毛を清潔に保ち、睡眠の質を向上させる効果があります。猫の健康を守るためにも、日光浴スペースは欠かせません。
南向きの窓の前に、クッションやお気に入りの毛布を置いてあげましょう。出窓があれば、さらに快適です。外の景色を眺めながらお昼寝できる場所は、猫にとって最高の特等席になります。
ただし、窓からの脱走を防ぐために、柵やネットを忘れずに取り付けてください。
まとめ——ペットも家族も幸せになる家づくり
ペットと一緒に暮らす家を作ることは、決して難しいことではありません。犬や猫の生態と習性を理解して、それぞれに合った空間を用意してあげれば、ペットも家族もストレスなく快適に過ごせます。
犬には、自由に動き回れる回遊動線、落ち着ける狭い専用スペース、そして家族の気配を感じられる場所が必要です。猫には、上下運動ができるキャットウォークや高い場所、爪とぎコーナー、そして一人でリラックスできるプライベート空間が大切です。
安全面では、滑りにくい床材、ペットフェンスの設置、危険な場所への立ち入り防止が重要です。掃除のしやすさを考えて、汚れに強い床や壁を選び、臭い対策として換気扇や消臭機能のある建材を取り入れましょう。
実際の施工事例からも分かるように、ちょっとした工夫で、ペットも人間も笑顔で暮らせる理想の家が実現できます。広い土間、回遊動線、ペット専用の足洗い場、キャットウォーク、日向ぼっこスペース——これらは決して贅沢なものではなく、家族全員が幸せに暮らすための「必要な投資」なのです。
あなたも、愛するペットと一緒に、毎日を笑顔で過ごせる家を作りませんか?家づくりの専門家に相談しながら、理想の「ペット共生住宅」を実現しましょう。
窓辺で気持ちよさそうに眠る愛犬、キャットウォークで伸びをする愛猫、そして家族全員の笑顔——それが、これから始まるあなたの新しい暮らしです。
1つのモデルハウスの見学時間は1時間以上をお勧めいたします。余裕を持って、当日の予定を組みましょう。
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。